"Scientific Research in Kyushu University", No.15, 25.3.1998
Wolfgang MICHEL(ヴォルルガング・ミヒェル)
17世紀後半の日欧文化交渉とカスパル・シャムベルゲル |
今日の異文化間理解や平和的共存の問題の多くは、その歴史的背景を考慮することなしには解決しない。逆に、歴史学に異文化的な観点を導入することにより、ある現象についてその動機や影響に関して、新たな見識を得ることができる。歴史は過去も現在も地球規模で進行するからである。筆者がこういった立場から研究している東西文化交渉におけるテーマの一つは、古書を読むうちに偶然発見したものである。1668年発行のある書物の脚注に、かつてその外科術のために日本の高官たちの間で非常に高く評価された、カスパル・シャムベルゲルという人物が、帰国後、ライプチヒで裕福な商人になっていることが記されていた。
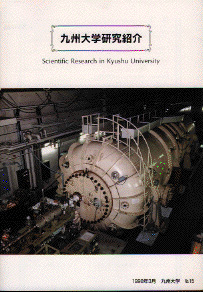
ヨーロッパにおいて忘れられたこのシャムベルゲルの名は杉田玄白が『蘭学事始』で言及して以来、日本の学術論文、専門書や百科辞典ではたびたび紅毛流外科の元祖として讃えられていたが、約100年にも亙ろうとする研究史にもかかわらず、その人物や行動の詳細は不明のままであった。上記の脚注から始まった調査はドイツ統一前のライプチヒ(旧東独)や、東インド会社の資料が保管されているオランダや日本にまで広がった。その範囲は結局シャムベルゲルの経歴のみには留まらず、数多くの後世の資料と混ざってしまった江戸時代の写本から、慶安2〜4年(1649〜51)出島蘭館の医師を勤めたシャムベルゲルの元来の「教え」および、「カスパル流外科」が誕生した当時の状況を次第に明らかにすることができた。いわゆる蘭学が始まるずっと以前に、30年戦争で鍛えられた、人柄もよく優秀な外科医シャムベルゲルと出会あった大目付井上政重筑後守や、後に老中になる稲葉政則など、先見の明のある幕府の人物は、西洋の外科学や本草学、薬学、蒸留技術、道具などを日本に導入する計画を進めるようになった。
 図1 晩年のカスパル・シャムベルゲル |
;歴史的発展に多様な要素が影響を与えることはここでも確認できる。その一つとしては偶然というものを挙げなければならない。寛永3年、3代将軍家光が重病になったので、オランダ側の特使一行は謁見のため何ヶ月も待たされていた。この間に侍医たちの手におえない持病に悩んでいる高官たちは、次第に江戸の「長崎屋」にいる外国人外科医の医術や薬品に目をつけるようになった。また、構造的な要素も重要な役割を果たした。海外との交流がわずかな相手に制限されたことで、数種の商品や外界関係の情報に対する依存感も強まっていた。紅毛人の医薬学の導入は官吏の健康のためばかりではなく、国内の医療の発展と、それにより体制の安定化にも役立ちそうだった。よく効く薬草を国内で栽培し、薬油などを生産するようになれば、以前から続いている薬品輸入に対する依存をいくらか和らげることもできる。さらに、個人の知識や先見性、影響力、決断力も見過ごしてはならない。内外の動きに精通していた大目付井上政重なくして万治頃までの計画的な「技術移転」の試みは説明できない。オランダ側の反応も興味深い。利益を重要視する史上初の株式会社VOCは日本側の「ノウハウ提供」の要求に対してかなり消極的であった。要求に応じていたのは、交易上の摩擦から関係改善のためにさらなる努力が不可欠になった時のみである。また、出島や江戸での異文化間コミュニケーションの困難も過小評価すべきではない。紅毛人の日本語学習は望ましくないとされていたが、そもそもポルトガル語を得意としていた日本人「通事」は元禄時代までオランダ語の日常会話のレベルを越えられなかった。オランダ語や、時にはラテン語版でもたらされた書物を読み、正確に理解するにはとても不十分だったので、やむを得ず、出島蘭館医に口頭で説明させることになる。商館長日誌に記されているように、この指導は双方にとって悪夢のようだった。江戸の「大物」の依頼で、出島の全通事が何週間も何ヶ月もかけて、説明を理解し、整理した結果、驚くほど短い報告書しかまとまらなかった。紅毛流外科の初期の写本に見られる数多くの片仮名表記の用語が当時の翻訳上の困難を物語っている。また、理論について極めて簡略的に述べながら、療法や処方などに重点を置くやり方も、この学術移転の限界を示している。したがって西洋医学の哲学的な背景は知るよしもなく、16、17世紀におけるこの学問の急激な発達さえも伝えられなかった。このように後世の蘭学のレベルには程遠いものだったが、シャムベルゲルとその後の出島蘭館医たちが紹介した医術はほんの20年の間に「紅毛流外科」として全国に根を下ろした。また、「鎖国」直後の日本が、これほどひたむきに西洋のノウハウを習得しようとしたことも大いに注目に値する。
(平成8年6月17日、日本医史学会奨励賞受賞)
Caspar Schamberger (1623 - 1706) und die eurojapanischen Kulturkontakte in der der zweiten Haelfte des 17. Jahrhunderts
Ueber Schamberger, erster Stammvater einer 'Chirurgie im Stile der Rotschoepfe' (= Hollaender), war lange nur wenig bekannt. Durch Kombination zahlreicher neuer Quellenfunde in deutschen, niederlaendischen und japanischen Archiven konnten nicht nur Leben und Reisen weitgehend aufgeklaert werden. Nach und nach wurde deutlich, dass Schambergers Begegnung mit fuehrenden Vertretern des Tokugawa-Regimes ein starkes Interesse an westlicher Medizin, Pharmazeutik und Kraeuterkunde ausgeloest hatte. Zwar entwickelte sich aus den importierten Instrumenten, Geraeten, Buechern, Samen, Pflanzen, Medikamenten und den zahlreichen, durch die Chirurgen der hollaendischen Faktorei Dejima erteilten Instruktionen noch keine autochthone 'Hollandkunde'. Doch fand hier unmittelbar nach dem 'Abschluss' Japans gegenueber der Aussenwelt ein von oben gesteuerter Versuch eines Wissenschafts- und Technologietransfers statt, der bereits zahlreiche Elemente der Modernisierungsbewegung des 19. Jahrhunderts enthaelt.
図2 膏薬の処方(、左『アムステルダム薬局方』1639年版、右「阿蘭陀医方秘伝」)
図3 出島で薬用油を製造するための蒸留装置(寛文12年、1672)
図4 ガレノス流の体液論の概略(ウモル<humor = 体液 /サンキ< sanguis = 血液 /コレラ< cholera = 黄胆汁/ヘレマ < phlegma = 粘液/マレンコンヤ< melancholia = 黒胆汁)


