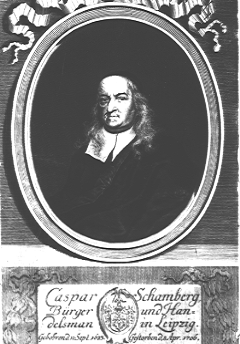Dejima rankan-i Caspar Schamberger no shôgai ni tsuite [On the Life of the Dejima Factory Surgeon Caspar Schamberger]. Journal of the Japan Society of Medical History, Vol. 36, No. 3 (1990), pp. 201-210.
出島蘭館医カスパル・シャムベルゲルの生涯について |
彼に因んで名付けられたカスパル流外科の父としてカスパル・シャムベルゲル( Caspar Schamberger )は日本の医学史上もっとも著名な人物に属している。これはキリスト教の世紀に、イベリア半島の宣教師によってもたらされた「南蛮流外科」に次ぐ最初の流派で、さらに「紅毛派流外科」が続き、その影響は19世紀の開国にいたるまで次第に大きくなっていった[1]。1649年から1651年まで滞在し、オランダ東インド会社で勤務していたその元祖ともいうべきカスパルは、後世に与えた影響を決して知ることはなかった。出島商館の業務日誌やその他の文書は、彼の活動について所々でふれてはいても、たいていは単に「 chirurgijn 」(外科医)とだけ記してある。普通だったら彼の名は世に知られるようにはならなかっただろう。しかし1649年特使アンドリース・フリーセ(Friese / Frisius)と江戸へ行き、徳川家光の謁見をまっている時、思いがけないことが起こる。シャムベルゲルと使節団の仲間3人は、使節団が長崎へもどっても、しばらく江戸にいるよう幕府側から要請された。こうして彼は合わせて約10ヶ月、通常は極めて閉鎖的な国の政治的中心地に滞在し、病人の治療や日本人医師の指導にあたった。彼は多大な報酬を得て長崎へ戻り、次の江戸参府にもあらためて参加した。そして1651年秋には日本を離れている。彼の日本人弟子やその著作も日本医史学の文献にはしばしば現れる。特に日本の研究者はこれについて詳細な分析を行っている。それに較べると、シャムベルゲルに関する数少ないヨーロッパでの研究は、興味をひくものがない。しかし、研究されているのは日本での2年間だけで、シャムベルゲルの残りの人生や出身地についてはほとんどわかっていない。彼の正確な名前さえ文献によって様々であり、その結果、いろいろな記述が見られる。筆者派、これまで知られていなかったシャムベルゲルの経歴について、クリスティアン・アルノルト( Christoph Arnold )編で1672年に出版された論文集『三大王国、日本、シャム、朝鮮について』をよんでいて手掛かりを得た。日本についてはここでは元平戸商館長カロンが主に書いている。アルノルトはフランソワ・カロン( François Caron )の日本論に対するハインリッヒ・ハーゲネル( Heinrich Hagenaer )の注釈を加えている。医学のことは商人であるカロンにはそれほど重要でなかった様なので、自分でも日本をよく知っていたワーゲネルが注を付けている。
百科全書的な野心を持っていた学者である編者アルノルトの目から見れば、このような記述はまだ不十分だった。彼は手に入る日本文献を読み、帰郷者や東インドを知っている人と接触氏、あちこちに詳細な注釈を加え、中には本文より長いものも見られる。この箇所の注は、こうなっている。
アルノルトはシャムベルゲルの所在地のみならず、彼が本来の職を辞し、今度は大商人になっていたことも知っていた。この情報はおそらく先の引用中にふれられているドイツのヴィンスハイム Winsheim 出身のヨハン・ヤコブ・メルクライン( Johann Jakob Mercklein )によるものだろう。メルクラインは1644年から45年にかけて、やはり理髪外科医として東インド会社で働いていた。51年、彼の船ポーランド王号( Koning van Polen )はシャムを出港し、8月3日から11月1日まで中崎に寄港していた。同僚であり、同胞でもあった彼はシャムベルゲルとこの時期、密に交流があったはずだし、さらにオランダ人は活動の自由が厳しく背限されており、この滞在は辛抱を強いられるものだった。アルノルトの伝えるエピソードでは商館にいたシャムベルゲルを「 Oberbarbier 」(上位外科医)と呼んでおり、彼は入港した船の不幸な同僚たちを、身分の高い日本人の治療のために、順々に長崎の町へ連れて行った。その中にはメルクライン自身もいた、おそらく、もっと見物したかっただろう。ポーランド王号がバタフィアに向かって出港したとき、前商館長ビーテル・ステルテーミウス( Pieter Sterthemius )とならんで、ヨハネス・ヴンシュ( Johannes Wunsch )と交代したカスパル・シャムベルゲルもおそらく乗船していたと思われる。旅は51年12月12日まで続いた。メルクラインとシャムベルゲルとの交流は二人の帰国後も途絶えることはなかったようである。でなければライプツィッヒの指摘は亡かっただろう。シャムベルゲルはしたがってオランダ人ではなくドイツ人である。実際ライプツィッヒ市公文書館での調査で、このことが確認された。1639〜83年の戸籍簿に次のように記載されている。
つまりシャムベルゲルはずっと出生地の市民であったわけではなく、1658年帰国後にやっと市民権を得た。父バルタザール・シャムベルゲル( Balthasar Schamberger )が1624年8月13日に市民権を得たことは1612〜66年の戸籍簿に記載されている[6]。ワイン商人としてふらんけん地方のケーニッヒスベルク( Königsberg )からライプツィッヒに移住した父親は、1622年9月3日に、同市の商人の娘マルタ・フィンジンゲル( Martha Finsinger )と結婚する[7]。長男カスパルは1623年9月11日に生まれ、翌日トーマス協会で洗礼を受けている[8]。
バルタザール・シャムベルゲルは1629年すでに亡くなっているが、未亡人は猶予期間の後、1632年5月24日に再婚している[9]。このような状況は、若いカスパルが東インドで運を試そうと決心する原因の一つにもなったのだろう。さらに、ライプツィッヒが30年戦争によって再三にわたり損害を蒙ったことも忘れてはならない。
シャムベルゲルは58年に出生地ライプツィッヒの市民権を得ているので、遅くとも1657年の帰国船でバタフィアを後にしているはずである。彼が日本の医学史上で果たした重要な役割から、彼が大学教育を受けた医師であったと思いがちだが、しかし博士号ならライプツィッヒの記録に記されていたはずだし、また正式に開業できる医師の免許があれば、故郷でもある程度の高収入と社会的な名声を得ることもできたであろう。しかし彼は帰国後、商人としての地位を選んでいる。したがって、おそらく彼は、東インドでは理髪外科医として働いていたのではないだろうか。東インド会社の商人たちはその記録に Barbierをたいてい Chirurgijn つまり外科医として記している。
15、16世紀のライプツィッヒには理髪外科医の組合があったことが証明されており、さらにマイスターになるためには16世紀には11年間の勤続年が必要だった[10]。17世紀も同じだったようである。彼の外科医としての教育については判断できないが、年齢的に8〜10年の外科医修行は可能だっただろう。船医として求職する際にオランダでは東インド会社の委員会で試験を受けることになっていた。アムステルダムは、その外科医組合にひ比較的厳しい基準を設けていた。応募者にはランセットの扱い、3杯の瀉血、外科術と道具についての問答や屍体の解剖が要求された。適当な屍体が足りないとき、解剖はおこなわれないことも多かった。また、ミッデルブルフ( Middelburg )では1648年頃でも、一定の金額を払えば合格できた[11]。
彼の半生の記録ではシャムベルゲルは「市民にして商人」( Bürger und Handelsmann )として登場する。ライプツィッヒ市公文書館にある、1669から98ねんのほとんどの関連資料んは、訴訟が記録され、それらは全部で1230ページになる[12]。シャムベルゲルの家庭生活も変化に富んでいた。1659年1月25日商人ドゥーゼル( J. C. Dusel )の、26歳になる未亡人と結婚した[13]。長男はまだ妊娠中に死亡し、次男は1661年3月6日に生まれたが、4月4日までしか生きなかった。夫人は出産後しばらくして、3月19日に亡くなった[14]。ケーラウ( Gerau )の商人の娘、17歳のレギーナ・マリア・コンラート( Regina Maria Conrad )との再婚は、1661年11月25日、ニコライ教会の近くにあるグリミッシュ通り( Grimma[i]sche Gasse )のシャムベルゲル家で行われた。この婚姻によって、シャムベルゲルは市の名士になった。義父は市議会に関係しており、聖ヨハニ病院の院長であり、商人だった[15]。二人は男の子が6人、女の子2人が生まれたが、息子3人と娘ひとりは幼くして死んだ。レギーナ・マリアは1684年11月10日まで生きた[16]。62歳になる頃、カスパル・シャムベルゲルは、ゴットフリート・シュライヒェル( Gottfried Schleicher )の未亡人、39歳のオイフロジーネ・クライナウ( Euphrosine Kleinau )を妻にスル。子供は亡く、数年の後婦人は1688年5月18日に亡くなった[17]。シャムベルゲル自身は当時としては驚くべき長寿で、83歳まで生きている。ライプツィッヒの埋葬記録には、彼が死んだのはグリミッシュ通りで1706年4月8日と記されている[18]。
子供たちのうち医史学上興味深いのはレギーナ・マリア・コンラートとの間1666年生まれたヨーハン・クリスティアン・シャムベルゲル( Johann Christian Schamberger )である[19]。父カスパルはこの息子が職業を選ぶ際に、若干の影響を与えたと思われる。ヨーハン・クリスティアンはまずフライベルク( Freiberg )で鉱山学を、続いて医学をアルトドルフ( Altdorf )とオランダのライデンで学び、1689年ライプツィッヒ大学で博士号を取った[20]。さらにとりわけ開業医学、助産法、自然科学を学んでいる。1693年に同大学医学部の助手( Assessor )、それから化学の助教授、生理学の教授、そして解剖学の教授になった。珍品陳列室( Cabinet von raren physikalischen Sachen )の持ち主として実験の演習( Collegia experimentalia )を行っている。ライプツィッヒ大学では新しい解剖教室を設立氏、学長にも選ばれた。カタリーナ・エリーザベット・シャッヘル(Katharina Elisabeth Schacher)と結婚氏、子供が4人生まれている。最後の子は祖父の名を取ってカスパル・フリードリッヒ( Caspar Friedrich )と名付けられた。末子のゴットヘルフ・アブラハム( Gotthelf Abraham )という名には長寿願いが込められているようだ。父親の健康状態はあまりよくなかった。1706年7月27日に遺言し、8月4日、父カスパルの死後4ヶ月足らずのうちに、40歳で没した。18世紀に出たツェードラーの著明な百科全書によれば、彼は在職中に死亡したライプツィッヒ大学の3人目の学長だった[21]。8月30日に行われた身分相応の壮厳な葬式に付いては、様々な文書に詳しく記されている。1714年に発行されたヨーハン・ヤコブ・フォーゲル( Johann Jacob Vogel )の『ライプツィッヒ年鑑』には父カスパルの肖像も載っている[22]。膨大な遺産をめぐる争いは記録によると1750年まで続いている。カスパル・シャムベルゲルとその息子が相次いで没したため、借金の返済規定や財産の相続が非常に複雑なもにになってしまったためだろう。
Jacob Vogel: Leipzigisches Geschichts-Buch Oder Annales [...] biss in das 1714. Jahr. Leipzig 1714 より。ライプツィッヒ市博物館蔵。
すべての東インド旅行者が夢みる冒険と富を、シャムベルゲルはほぼ手中にしたといえるだろう。だからこそ不思議に思えるのは、このような人が何も書き残さなかったことだ。はるかに経験の浅いドイツ人たち、フォーゲル、ザール( Vogel, Saar )、メルクラインは、友人や知人に求められてかなりの記録を残している。運良く、筆者はこの点でも、シャムベルゲルの手書き原稿か、もしかしたら印刷物があるという証拠を突き止めた。ドイツ・ギーセン( Gießen )のヴァレンティーニ教授( Michael Bernhard Valentini, 1657-1729)は18世紀初頭に博物館またはあらゆる物質と香辛料の劇場という医学的、文化史的に興味深い著作を出している[23]。いろいろな植物やあらゆる国々の医薬品に関する論文で、読書家のヴァレンティーニは「選定した書物と著者の概観」( Conspectus Librorum et Autorum Allegatorum )を前提にしているが、残念なことに当時の文献表示ではほとんど要約されてしまっている。ヴァレンティーニはこの表のなかで「 Schamberger's Japonische Reiß=Beschreibung 」、つまり「シャムベルゲルの日本旅行記」を挙げている。残念なことに彼はその全著作中でシャムベルゲルの名についてはここでしか触れていないようである。だから彼がどこでシャムベルゲルを参考にしたのかは想像するしない。おそらく、シャムベルゲルは、日本の植物、薬草や薬品について何かを書いていたのだろう。ヴァレンティーニはその出典がシャムベルゲルの印刷物からであったか、それとも手書き原稿からであったかを明白にしていない。したがって手書き記録からの出典の可能性も否めない。この史料の所在については、いろいろと手を尽くしてはいるが、これまでのところまだ手掛かりを得ていない。
注釈