Wolfgang Michel: Ibunka to no deai -- Oranda kapitan no "ekken" ni tsuite [Intercultural Encounters -- On the "Audiences" of the Dejima "opperhoofd"]. Yôgakushi Kenkyû - Journal of the History of Western Learning, No. 15 (Tokyo, April 1998), pp. 1 - 11. (「洋学史研究」第15号、1998年4月、1~11) Due to HTML-code problems some features have been changed. A pdf-file of the original printed version is available on the Kyushu University Institutional Repository. |
異文化との出会い ー オランダ・カピタンの「謁見」について |
エンゲルベルト・ケンペルの『日本誌』に見られる記述の中でヨーロッパ人の想像を特に刺激したのは、1691・92年徳川綱吉との公式の謁見後に行われたオランダ人の歌、踊り、演技を中心とする「第2幕」についての紹介であった。[1] 日本の「皇帝」とオランダ人との出会いのイメージを決定的なものにしてしまったこのケンペルの記述は18世紀の作家たちによってよく利用され、シーボルト来日の19世紀初頭に至るまでヨーロッパにおける日本像の重要な一部と見なされたのである。元禄期の上記の「第2幕」について調べたところ、[2] 5代将軍綱吉が即位する以前から多くの出島商館長は江戸参府中の本来の公式謁見についても、かなり不満を持っていたようだ。本論文においては、その不満の原因となっていたものを追究することにする。
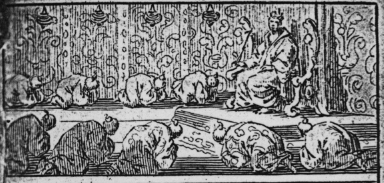
「Audientie」
封建時代のヨーロッパに遡ってみても、たいていの国では支配者との公式の会見は厳しく規制されていた。その場合のやりとりは例外なく、儀式的な性格ゆえに非日常性が強調されている。ローマ帝国の時代から、謁見を表す語として「 audiencia(西), audience(英), audiëntie(蘭), Audienz(独)」などという言葉が受け継がれてきたが、これは「注意」や「傾聴」の意味を表すラテン語の「audientia」という名詞から派生している。誰かの言葉に耳を傾けるということは、ある程度空間的な接近を前提としており、また、相手から話しかけられるということをも示している。しかし、発言権は平等に割り当てられていたわけではない。支配者は謁見者に比べるとほとんど規制を受けず、またそれをいつでも設定しなおすことができた。さらに西洋の謁見のもう一つの特徴は直接的なアイ・コンタクトにある。これは尊敬と服従の意を表すために必要であった。ローマ法王や大司教たちの指輪にくちづけをする場合もあり、身体の接触しない謁見に比べると、この場合は感情を伴う関係が生まれやすいということになる。
また謁見は、その機会を一定の人物や一定の社会的地位に限定することにより、公認、称賛や表彰の表明という機能をも果たしていた。支配者は時々謁見を利用して身分階級を一時的に無視し、低い身分の者にも機会を与え、そうでもしなければ耳に入らないような要望などを述べさせることもあった。しかし謁見はほとんどの場合、支配者と選ばれた人物との間の一定の状態や社会的な関係の継続を確認したり、また逆に、この両者の間の状態に変化が生じたことを確認するために行われるものであった。
服従の意を身体で表現するのは西洋でも日常的なことであった。例えばケンペルの故郷リッペの侯爵のように小国の支配者の前でさえ、帽子を取り、深くおじぎをして、許された時にだけ話すことができた。このようなわけで、歴代の商館長には江戸城にどんな心づもりで臨んだらよいのかはっきりわかっていた。商館長は会社の代表として、日本での商業活動が許されたことに対し、献上品を差し上げながら謝意を表し、この状態が今後も続くことを願い出るのである。もし日蘭関係上の問題が起これば通常、謁見の前に長崎奉行や大目付、あるいは老中と交渉し、最終的な解決法が見つかってから謁見を申し出た。
東インド会社がこの謁見をどれほど重要視していたかは、1634年の出来事によく表れている。この年の5月、ポルトガル人の代表団も例年の謁見を中旬に行う予定だった。オランダ人の謁見は月末に計画されていたが、平戸商館長クーケバッケル(Nikolaes Coeckebacker)はあらゆる手段を用いて、なんとかポルトガル人と同じ日に謁見が行われるようにした。謁見の順番をくつがえすことは出来なかったが、当日ポルトガル人を見下しながら城内の控えの間で上座についていたオランダ商館長一行は、その勝利を得た喜びを記録に残している。[3] 会社の代表である彼らにとって、旅や献上品にかかる毎年の費用は悩みの種であることには違いなかったが、それでも将軍への謁見は望んでいた。有名なブレスケン号事件のため幕府は1648・49年には謁見を許可しなかった。すると東インド会社はあわてて莫大な費用をかけ特別使節団を日本へ送り込んだが、このことからも上記の姿勢がよく窺える。[4]
江戸城の控えの間(vertoefzaal)で待つということは、西洋の習慣にもかなっている。すべては礼式に則って進行するわけであるから、最後の用意をして待つことになり、それは同時に、これから起ることが日常とは異なる出来事だという意識を高揚させることにもなるのである。かなり長く待たされることもあり、時には3、4時間かかったと書いている商館長もいる。[5] この控室にはさまざまな人物が姿を見せ、非公式に接触することもできた。彼等の名前は明かされていないことも多いのだが、ヨーロッパ人にはまわりの人たちの様子から、それらの人々が身分の高い人物だとわかったようである。
日本、とりわけ江戸城では外国人との出会いの機会は極めてまれだったため、異常な興味を示す人も少なくなかったようである。多くの場合、進行の責任者はそれをふさわしからぬ迷惑と見なし、それ相応の対策をとった。
「我が国の人は数人年々ここに現われるが、その人や服装を、ヨーロッパで象その他珍しい動物を見物するように見ようとする人たちが室内に入ることを妨げるため、宮中の係員三人が室外に配置されていた。」[6]
長崎奉行のような大物が自ら屏風を取り、一般の人々の通行を防ぐためにそれを廊下に置いたという記述さえ残っている。[7]
控えの間の内装が印象的だったことは、次の文面からも窺える。
「当番の上士が数人身分の順に坐っている。その側を通り、襖で隔離した広間に入って待った。この室は奥行36間で、[8] 周囲の襖には獅子、樹木、小山などの絵が描いてあり、高さ1間の所には、孔省、雁、花などが彫ってあり、その上から奥の広間の天井が見えた。その天井は我らのいた室と同じく、方形の板に金を塗り、種々の絵を描き、縁の枠が添えてある。」[9]
最後に商館長のみが控えの間から謁見用の大広間に案内される。商館長が途中で、次のように急かされることもあった。
「ここで尚2時間待った後、我々は「速く、速く」と呼ばれた。」 [10]
「筑後殿と喜右衛門の後から廊下を、大目付にハヨウ、ハヨウと急かされて、突き出た丸い屋根の下の宮殿の外側の通路を進み、かどを2回まわって多数の人の坐った広間を過ぎ進物の並べてある板敷の所に急いで坐らされたが、・・・・・・」[11]
大広間へ向かいながら江戸城の様子を注意深く観察する余裕を持っていた館長もいた。
「それから、諸公が皆呼ばれて各々その位置に着さ、予も亦呼ばれて室を出て筑後殿と山本平九郎殿とに導かれ廊下を通って、右には少数の人が居た広間を、左には青い小石を敷いた建物の上部を見ながら進んだ。廊下の行止りには甚だ広い建物が突出していて、その外側に手摺のついた幅1間半の縁側があり、それを通って建物を廻り、内部の整頓するまで少し待って、通詞と共に山本平九郎殿に導かれて第2の隅まで行き、来れという言葉を聞いてそこを廻り、4、5間進んで建物の他の側に出ると、筑後殿が来て諸公に敬礼せず、合図のあるまで真直ぐに陛下の前まで進むよう注意した」[12]
ときには商館長の2、3の同伴者に、廊下から謁見の間の様子を覗くことが許可されることもあった。謁見自体については17世紀後半の商館長の多くは、その目的はわかっていたものの、それに満足してはいなかったようだ。同じ場にいるというのに、将軍は御簾の向こう側に坐り、たいていはその輪郭しか見えない。このようにアイ・コンタクトが制限されると、ヨーロッパ人は人格を無視されたと感じてしまう。初期の顕著な例として、商館長ハッパルト(Gabriel Happart)の日記には、1654年3月16日付の箇所にこう記されている。
「そして私は殆ど偉大な皇帝を見上げる暇もなく、来た時と同じように急かされて前の室に帰った。次に宮殿の入口に行き、そこで筑後殿と喜右衛門殿の祝福を受け、正午前に宿に着いた。これが我らの常に日本の陛下の謁見と称するもので、むしろ屈従陋劣な敬礼と言うべきものであるが、当地では非常に重視され、この国の人数千否数百万には決して許されぬものであり、このためには顧問官[= 老中]や筑後殿、喜右衛門様の大なる尽力を要したのである。」[13]
これ以前の蘭館日誌には御簾のことを指摘する記述はまだ見つかってはいない。また、例えば1643年12月11日付の日記には商館長エルセラック(Elseracq)が書き留めたように、将軍の着衣や外見についての描写さえ窺える。
「その後しばらくして予一人呼ばれ、大目付から前に示された陛下の王座の前に導かれた。陛下は黒い絹の上衣を着て頭には黒い頭巾を被り、立派な高い座に着いて居られ、見たところ丈の低い痩せた人であった。筑後殿はカピタンよ、陛下に敬礼感謝せよと言い、終って予の服装が見えるようマンテルを開くことを命ぜられた。しばらく坐っていた後、大目付に外套を引張られ、いざりながら退出し、他のオランダ人と共に最初控えた室に帰った。」[14]
1650年代に至るまでの記述には、以下のようにある種のアイ・コンタクトを思わせる例が多数現れており興味深い。
「皇帝は非常に多数の人々を従え、3段の高座の上に、真中に一人で坐っていた。」(1636年3月5日)[15]
「陛下は黒い絹の上衣を着て頭には黒い頭巾を被り、立派な高い座に着いて居られ、見たところ丈の低い痩せた人であった。筑後殿はカピタンよ、陛下に敬礼感謝せよと言い・・・・・・」(1643年12月11日)[16]
「そこには顧問官たち[= 老中]が居り、陛下は奥の一室に居られ、襖が約1フート半開いていた。」(1646年2月12日)[17]
「陛下[= 家光]が、その座席から頭と体を前方に屈して居られたのを少し戻された時に、敬礼をしたところ、他の進物の並べてある室に四間半離れて平伏していた安藤右京殿が、ロを開け大声で、オランダ・カピタン・ウイルレムと言った。陛下は広間の正面の室に、王座もなくまた少しも高くしてない畳の上に膝を屈して坐り、頭には冠り物もなく、着物は黒衣に青い網をかけて、他の人たちと少しも違わない。色は白く立派で、体はむしろ痩せた方、丈は少し高い方、顔は長い方で、年齢は42歳であるが、40より上には見えぬ。」(1647年1月6日)[18]
「陛下が顧問官2人の間に一段高くなった所に着坐されるのを見て、敬礼するよう注意された。予がしばらく体を屈めていた時に、大官の一人、通訳の想像では安藤右京様の発声で、オランダ・カピタンと呼ばれた。」(1652年2月7日)[19]
「20から25フートの所に、黒い服装で直立して居られた陛下を見て、予は頭を下げた。」(1653年2月12日)[20]
「いくらか高い所に日本の君主は黒か、あるいは暗い色ともいうべき服装をしていた・・・・・・」 (1655年2月21日)[21]
「筑後殿が近づくよう合図をした。向きを変えて見上げると、日本の皇帝は高座に黒い服装をまとって・・・・・・」(1656年2月10日) [22]
「今回は2年前よりも長く陛下を見ていられた。見ていると、いくらか男らしくなられたようだ 」(1659年4月19日)[23]
「・・・・・・陛下はいくらか厚めのふとんに坐り・・・・・・」(1661年4月2日)[24]
「非常に大きな広間の向こうの端に、皇帝は一人、いくらか高い場所に坐って・・・・・・」(1662年4月19日)[25]
1663年以降は、上記のような記述が見当たらないので、オランダ人に姿を見せない謁見の形式が、寛文3・4年の頃からはじまったのではないかと推測される。[26] 唯一の例外として1674年(延宝2年)の記述があるが、そこに見られる将軍の幾つかの特徴は興味深い。
「彼は日本で言う中肉中背というよりもむしろやせ形でいくらか長身だった」 [27]
お辞儀や敬礼はヨーロッパの宮廷でも日常的に行われていた。ローマ帝国の時代から「Prostratio」という語があり、それは、およそ「身をひれ伏す」というほどの意味だった。しかし17世紀になるとこのような姿勢を取るのは、 カトリック聖職者の授任式の時や、精神的に絶望の淵に立たされるような場合のみで、そのような時でも、むしろ教会の祭壇の前でひれ伏すことはあっても、君主の前でなされることはなかった。江戸城での謁見に際する劇的でない、静かな「平伏」には、それを言い表すのに適当な語がないため、具体的に文章で説明しなければならなかった。
「予は大官たちの側の少し低い木の廊下に脆いて頭を低く下げていたが、顧問官讃岐殿も同じ様に頭を低く下げて高声にオランダ・カピタンと叫んだ。」(1646年2月12日)[28]
「脆いて頭を下げることを命ぜられた。」(1651年3月24日)[29]
「予がしばらく体を屈めていた時に、大官の一人、通訳の想像では安藤右京様の発声で、オランダ・カピタンと呼ばれた。」(1652年2月7日)[30]
「Prostratio」はそもそも西洋にも存在していたのであるけれども、17世紀にはそれは非ヨーロッパ的なものとなり、東洋の暴君の特徴と見なされるようになっていた。理性を有し自己確立したヨーロッパ人と本能的かつ未熟な子供である東洋人とを対比させる本格的なオリエンタリズムを産んだ19世紀になってから、この身をひれ伏す姿勢に対して、ヨーロッパでは中国語の「叩頭」から取り入れた「Kotau(独)、Kotow(英)」が用いられるようになったのもあながち偶然ではなかった。
江戸城の奏者番が「オランダ・カピタン」と呼べば、もっと低く頭を下げなければならない。また、商館長が直接言葉をかけられることもなく、このようなことはヨーロッパ流の傾聴するという意味での謁見では全く考えられないことであった。さらにまた謝意は西洋においては、日本とは異なり、言葉で表すものであって、黙っていたのでは感謝したことにはならないのである。
長崎から江戸へ至る約1200キロの旅の果てに与えられた、このほんの一瞬にすぎない「クライマックス」の終わりは、商館長の後ろにいる長崎奉行がそのマントをつまんで引っ張る行為によって商館長に伝えられたが、デリケートな「カピタン」はこのことに憤慨して、その気持ちを日記に書きとめている。また、身体の向きを変えずにゆっくりと廊下まで平身低頭して「退場」することについても、「はう」(cropen)[31] などの言葉を思いつく著者もいた。
商館長が控えの間に戻ると、そこにいる人々は無事に終わってよかったとお祝いの言葉をかける。容易に想像できることだが、日本側ではまじめに祝福しているつもりでも、何らかの行動や発言を自発的に行う機会が与えられなかったヨーロッパ人の耳には、それは奇妙に聞こえたに違いない。
結局のところ、東インド会社の代表者たちは江戸城でのこの儀式の重要性、必要性についてはっきり認識してはいたものの、その形式については当時のヨーロッパの習慣や自己像とかけ離れていたものであったため、最後には強い不満感が残ってしまったのである。このような出会いの名として、「audientie」はこの語の持つ本来の意味からして、不適当な言葉であったため、ヨーロッパの商館長たちの不満感はその後もずっと消えなかった。
参考文献
- Bernhardus Varenivs: Descriptio Regni Iaponiae / Cum quibusdam affinis materiae, Ex Variis auctoribus collecta et in ordinem redacta per Bernhardvm Varenivm Med. D. Amstelodami, Apud Ludovicum Elzevirium. Anno M.DC.XLIX (1549), 287 pp.
- Arnoldus Montanus: Gedenkwaerdige Gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in't Vereenigde Nederland, aen de Kaisaren van Japan [...] Amsterdam 1669.
- 永積洋子訳『平戸商館の日記』岩波書店、東京、第1~3輯、1969年(1980年、3)、第4輯、1970年(1980年、3)
- 村上直次郎(訳)『長崎オランダ商館の日記』(全3冊)岩波書店、東京1956年。
- 今井正翻訳、エンゲルベルト・ケンペル『日本誌 : 日本の歴史と紀行』東京1973年。
- ケンペル『日本誌 : 日本の歴史と紀行』(今井正翻訳)下巻、305~315、389~396頁。
- 「轟ヒ城に躍るケンペル 一 五代将軍綱吉と西洋人とのつき合いの諸問題」(洋学史研究会発表、1997年11月8日)。「異文化との出会い =@五第将軍綱吉の謁見について」(洋学史学大会発表、1997年12月7日)。
- 平戸・出島商館日誌(Dagregister)はオランダの国立中央文書館の出島商館伝来文書(ARA 1.04.21, Nederlandse Factorij Japan、以下NFJ)所収のものを利用した。「ポルトガル人と一緒に同じ部屋で、我々は上座に、彼等は下座に坐り」。NFJ 53: Dagregister Hirado, 6.9.1633 - 3.2.1639 (14.5.1634)。永積洋子訳『平戸商館の日記』第3輯、117~119頁。
- Dagregister Dejima 1647 - 1648 (16.1.1648). NFJ 62, Dagregister Dejima 1648 - 1649 (1.4.1649). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第2巻、238頁。
- NFJ 56, Dagregister Dejima 1641 - 1642 (22.1.1642). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第1巻、152頁。(待ち時間4時間)
- NFJ 67: Dagregister 1653 - 1654 (16.3.1654). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第3巻、283頁。
- NFJ 95: Dagregister Dejima 1681 - 1682 (5.4.1682).
- 34畳という記述もある。NFJ 68: Dagregister Dejima 1654 - 1655 (21.2.1655)
- NFJ 60, Dagregister Dejima 1646 - 1647 (6.1.1647). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第2巻、135頁。
- NFJ 53: Dagregister Hirado, 1633 - 1639 (3.5.1636). 永積洋子訳『平戸商館の日記』第3巻、348頁。
- NFJ 67: Dagregister 1653 - 1654 (16.3.1654). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第3巻、283頁。
- NFJ 60, Dagregister 1646 - 1647 (6.1.1647). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第2巻、137頁。
- NFJ 67: Dagregister Dejima 1653 - 1654 (16.3.1654). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第3巻、283頁。
- NFJ 58: Dagregister Dejima 1643 - 1644 (11.12.1643). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第1巻、286~87頁。
- NFJ 53: Dagregister Hirado, 1633 - 1639 (3.5.1636). 積洋子訳『平戸商館の日記』第3巻、348頁。
- NFJ 57: Dagregister Dejima, 1642 - 1644 (11.12.1643). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第1巻、286頁。
- NFJ 60: Dagregister Dejima, 1646 - 1647 (12.2.1646). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第2巻、75頁。
- NFJ 60: Dagregister Dejima, 1646 - 1647 (6.1.1647). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第2巻、138頁。
- NFJ 65: Dagregister Dejima, 1651 - 1652 (7.2.1652). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第3巻、109頁。
- NFJ 66: Dagregister 1653 - 1654 (12.2.1653). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第3巻、203頁。
- NFJ 68: Dagregister Dejima 1654 - 1655 (21.2.1655).
- NFJ 69: Dagregister Dejima 1655 - 1656 (10.2.1656).
- NFJ 72: Dagregister Dejima 1658 - 1659 (19.4.1659).
- NFJ 74: Dagregister Dejima 1660 - 1661 (2.4.1661).
- NFJ 75: Dagregister Dejima 1661 - 1662 (19.4.1662).
- 綱吉が即位する1681年までの以下の出島日誌には商館長が将軍の姿が見たという記述はない。NFJ 77: Dagregister Dejima 1663 - 1664 (24.4.1664); NFJ 78: Dagregister Dejima 1664 - 1665 (16.4.1665); NFJ 79: Dagregister Dejima 1665 - 1666 (19.4.1666); NFJ 80: Dagregister Dejima 1666 - 1667 (8.4.1667); NFJ 81: Dagregister Dejima 1667 - 1668 (9.4.1668); NFJ 82: Dagregister Dejima 1668 - 1669 (1.4.1669); NFJ 83: Dagregister Dejima 1669 - 1670 (20.4.1670); NFJ 84: Dagregister Dejima 1670 - 1671 (10.4.1671); NFJ 85: Dagregister Dejima 1671 - 1672 (31.3.1672); NFJ 86: Dagregister Dejima 1672 - 1673 (17.4.1673); NFJ 88: Dagregister Dejima 1674 - 1675 (26.3.1675); NFJ 89: Dagregister Dejima 1675 - 1676 (27.4.1676); NFJ 90: Dagregister Dejima 1676 - 1677 (18.3.1677); NFJ 91: Dagregister Dejima 1677 - 1678 (5.5.1678); NFJ 92: Dagregister Dejima 1678 - 1679 (11.4.1679); NFJ 93: Dagregister Dejima 1679 - 1680 (2.4.1680)。
- NFJ 87: Dagregister Dejima 1673 - 1674 (20.4.1674).
- NFJ 60: Dagregister Dejima, 1645 - 1646 (12.2.1646). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第2巻、75頁。
- NFJ 64: Dagregister Dejima, 1650 - 1651 (24.3.1651). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第3巻、49頁。
- NFJ 65: Dagregister Dejima, 1651 - 1652 (7.2.1652). 村上訳『長崎オランダ商館の日記』第3巻、109頁。
- NFJ 77: Dagregister Dejima 1663 - 1664 (24.4.1664).

